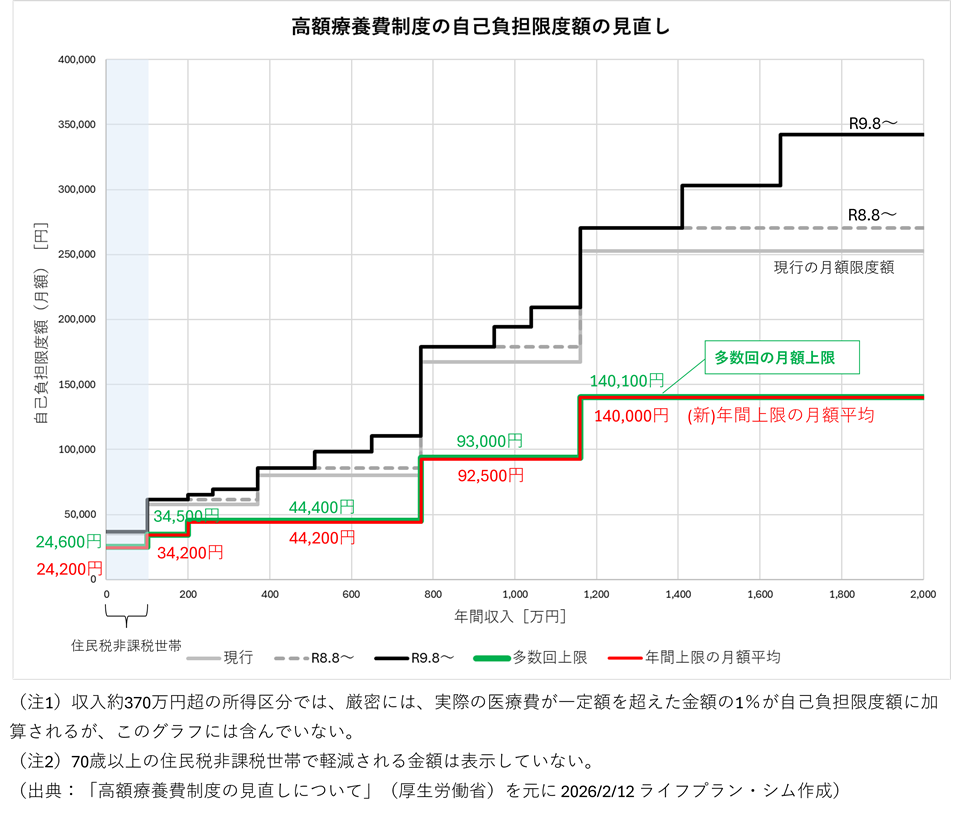最近の国会では、眠っている貯蓄を投資に回して経済を活性化させることが議論されていますが、いざ貯蓄を投資に回そうとした時に、一括で購入してよいのか、あるいは積立てた方がよいのか、悩む場合もあると思います。もちろん、一括での購入には、それなりの貯蓄がある場合に限られますので、必然的に積立てを選ぶ場合もあると思います。ここでは、どちらでも選択できる場合に、どのような違いがあるのかを見ておきましょう。ただし、ここでは比較を単純化するために、売買手数料や運用コスト、分配金などは、計算から除外して比較します。また、短期では特徴が表れにくいため、長期投資(少なくとも10年以上)を前提とします。
まず、一括購入では、売却時の基準価額(株価なども含む)が、購入時の基準価額を上回れば利益になり、下回れば損失になるという単純な特徴があります。安値で購入して、高値で売却することが基本で、その意味では、長期に見て右肩上がりの傾向にある相場や銘柄に対しては、効率的な購入方法になります。そうでない場合は、安値であることを様々な情報から見極めて購入しなければ、リスクが大きいと言えます。
一方、積立ては、特に定期的に一定金額を購入するドルコスト平均法では、値が下がった時に多く購入し、値が上がった時に少なく購入するという特徴があります。このため、値動きが大きくもみ合う相場や銘柄に対しては、リスクが低く抑えられます。しかし、一時的な値下がりには強いものの、上がってから下がった場合などでは損失が出る場合もあります。また、右肩上がりの場合には、一括で購入した方が利益が大きくなります。
グラフは、ドルコスト平均法で積立て購入した場合に、基準価額(赤色の折れ線)の変動の仕方によって、購入口数(灰色の折れ線)がどう変化するか、収益率(橙色の折れ線)がどう変化するかを示しています。①基準価額が単調に上昇するケース(左上)、②基準価額が変動しながら平均的に上昇するケース(右上)、③初回の基準価額よりも低い価額でもみ合い後に上昇するケース(左下)、④初回の基準価額よりも高い価額でもみ合い後に上昇するケース(右下)を示しており、全てのケースで初回の基準価額は10,000、10年後の最終回の基準価額は16,000(年利約5%の複利)としています。
一括で購入する場合は、10,000で購入して16,000で売却することになり、収益率は60%になります。これに対して、①のケースでは、収益率は約20%にとどまります。徐々に基準価額が上昇することで、購入口数が少なくなって行き、一括で購入するよりも収益率は低くなります。また、②のように基準価額が変動しながら平均的に上昇する場合も、①に収斂されて約20%になります。一方、③④のもみ合い後に上昇するケースでは、収益率は約40%~80%になっており、一括購入の60%に近づき、それを上回る場合もあります。
長期的に見て右肩上がりの銘柄はなかなか無いものですが、過去からの傾向を見れば、米国株式のインデックスに連動した投資信託などはこのような傾向を見せています。その意味では、一括購入でのリスクは低い方ですが、それでも、一時的に大きく下落したこともありますので、リスク許容度が高くないと気が休まりません。リスク許容度が低い方には、積立て投資をお勧めします。また、リスクを減らすためには分散投資も有効です。地域分散、さらには債券なども組み合わせてポートフォリオに含めれば、リターンは減るもののリスクも下がります。
本記事は、投資の際の購入方法を、一定の条件のもとで比較し、その特徴を示したものです。全てのケースにおいて同一の結果を保証するものでも、利益を保証するものでもありません。また、個々人によって、資産状況やリスク許容度も異なるものです。元本割れも含めて、投資のリスクを正しく理解した上で、ご自分で判断してください。
(注:本記事は2022/6/17に投稿しましたが、説明の範囲を広げてしまったことで、本質的な違いが分かりにくかったため、2024/5/28に内容を見直しました。)
関連記事:「投資信託のポイント」