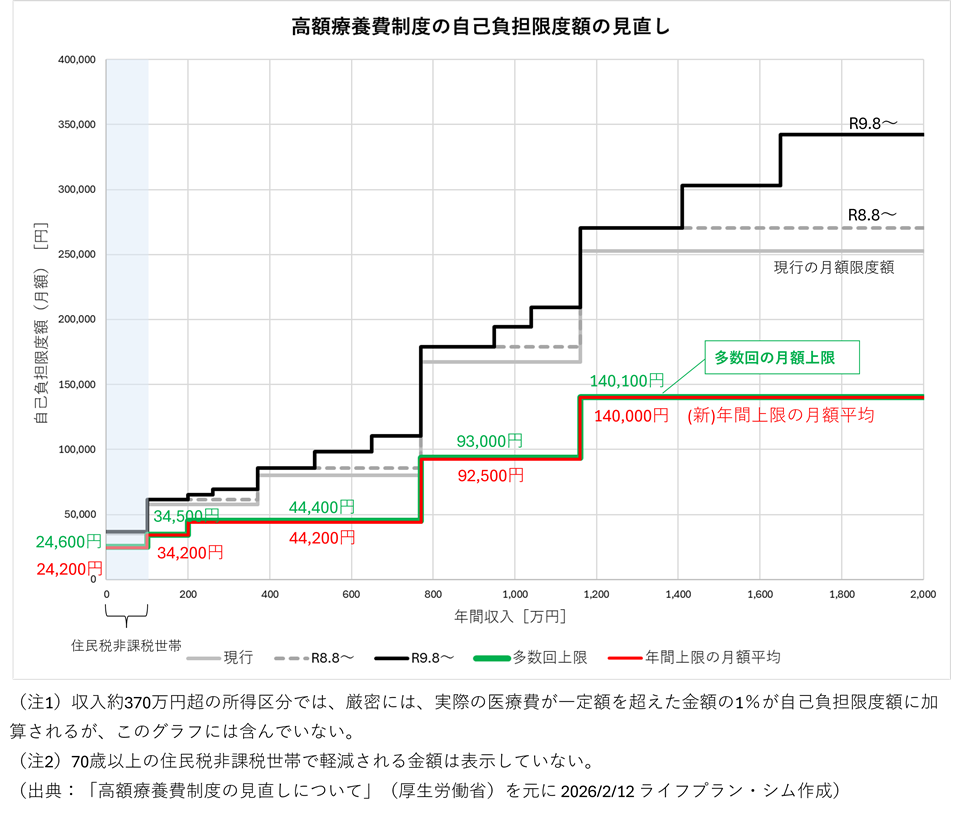確定拠出年金には、企業型(DC年金)と個人型(iDeCo)がありますが、どちらの場合でも一時金として受け取る方法と、年金で受け取る方法があります。その受け取り方によって、税金や社会保険料が変わってきますので、それを知った上で判断されると後悔が無いと思います。
一時金として受け取る場合は、退職所得として他の所得と分離されて扱われ、退職所得控除を受けられます。さらに控除後の1/2の金額に対して所得税、住民税が課税され、社会保険料は課せられません。退職所得控除は、勤続年数(端数切上げ、確定拠出年金の場合は加入(掛金の拠出)年数)に比例して増え、勤続年数が20年を超えると傾きが大きくなりますので、勤続年数が長いほど、一括で受け取ることで税額を抑えられる可能性があります。
さらに、一時金の場合、退職金の受取り時期によって控除が異なります。退職金と同時に一時金を受け取る場合には、退職金と一時金を合算した額が退職所得となり、勤続年数と加入年数のどちらか長い方が適用されます。例えば、勤続年数の方が長く40年の場合は、40万円×20年+70万円×(40年-20年)=2,200万円が退職所得から控除されます。なお、退職金と確定拠出年金が控除額以下であれば同時に受け取るのが良いと言えますが、控除額を超えて課税される場合には、退職金を受け取った翌年以降に確定拠出年金の一時金を受け取ると、同時に受け取るよりも節税になる場合があります。確定拠出年金は受け取った年の退職所得として税額計算されるため、退職所得控除は受けられなくても、退職所得が2年に分割されることで税率が低く抑えられる場合があります。なお、確定給付企業年金(DB年金)の場合は、翌年以降に受け取っても退職金と同じ年の所得として見なされるため、そのような効果はありません。
一方、退職金を受け取った後に、何年かして確定拠出年金を一時金で受け取る場合で、一時金を受け取った年の「前年以前19年以内」※に退職金を受け取っている場合には、退職所得控除から重複期間(端数切捨て)に相当する控除額を差し引かなければなりません。例えば、確定拠出年金の加入年数がトータル20年とすると退職所得控除は40万円×20年=800万円ですが、その5年前に退職金を受け取っていて、退職後も一時金を受け取るまで確定拠出年金に加入していたとすると、15年間の勤続年数が重複していることになり、15年の勤続年数に相当する控除40万円×15年=600万円を差し引いた800万円-600万円=200万円が実際の控除額になります。控除額を増やしたい場合は、退職後も少額でも掛金を拠出し続けることです。運用期間が増えただけでは控除されません。
ただし、前年以前19年以内に退職金を受取った場合でも、退職金が退職所得控除よりも少ない場合には、受取った退職金から逆算してみなし勤続年数を求め、重複期間を短縮することができます。具体的には、退職金が800万円以下の場合は退職金÷40万円で、800万円を超過する場合は(退職金-800万円)÷70万円+20年(端数は切り捨て)でみなし勤続年数を求めます。就職の日からみなし勤続年数までの期間と確定拠出年金の加入期間の重複期間を、確定拠出年金の所得控除の計算に用いることができます。(2023/7/18 追記)
年金として受け取る場合には、公的年金と同様に扱われますので、雑所得に合算されて公的年金控除が受けられ、それを超える分は、他の事業所得、不動産所得などと合算して所得税、住民税が課税されます。また、社会保険料も課せられます。どちらの受け取り方法を選ぶかは、まとまったお金がすぐに必要か必要でないかと、他の退職金や年金との兼ね合いでどれが最も節税になるかが焦点になります。
以上、節税の観点からは、退職金と確定拠出年金を合計して、退職所得控除額以下であれば、退職金と一緒に一時金で受け取るのがよいと言えるでしょう。退職所得控除を超えている場合は、退職金と一時金を別の年に受け取った方がよく、資金に余裕があれば、公的年金受給までのつなぎとして年金で受け取るとさらに節税になる場合もあります。また、確定拠出年金額が多ければ、つなぎの期間を増やし、老齢年金を繰下げ受給して増やしてもよいでしょうし、公的年金が少ないのであれば、退職後も加入期間をできるだけ増やして運用し、公的年金を補ってもよいでしょう。いずれにしても、個々のケースでどのような受け取り方が最適か、ライフプランシミュレーションで確認するとより安心です。
※令和4年3月31日以前は「前年以前14年」が適用された。また、退職金を続けて受け取る場合は「前年以前4年」が適用される。先に確定拠出年金の一時金を受け取り、後に退職金を受け取る場合は「前年以前4年」が適用される。
(出典:「No.2735 同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2735.htm)、
「No.5231 確定給付企業年金等に係る課税関係」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5231.htm)を元にライフプラン・シム作成)