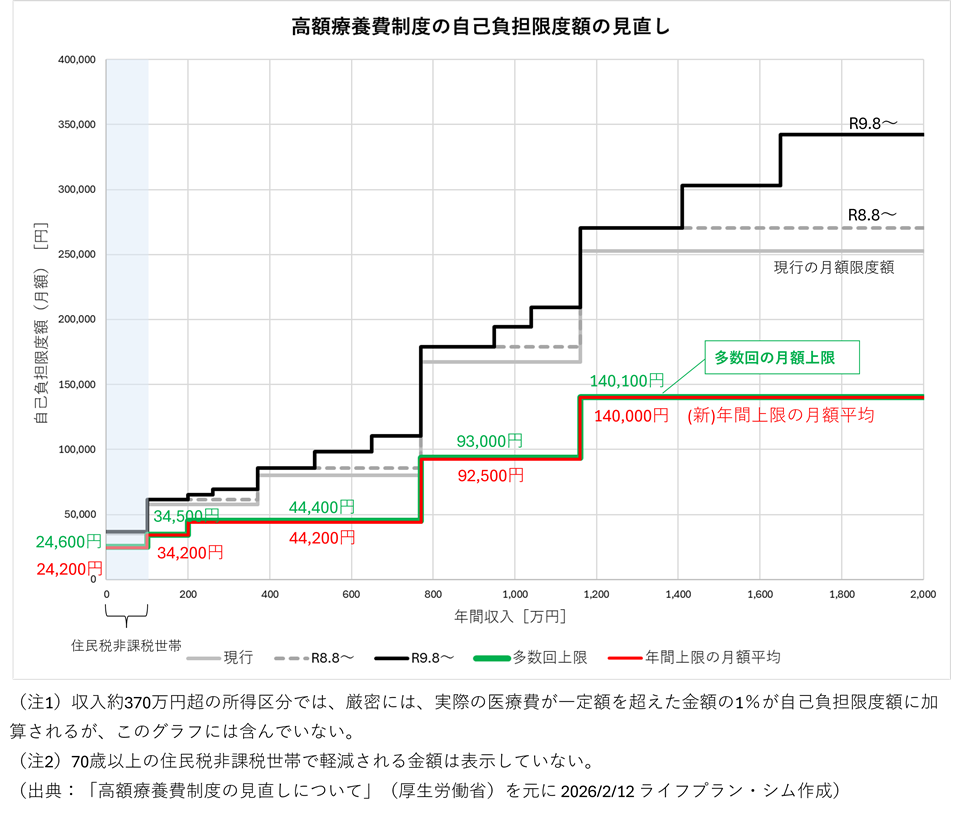国民年金の保険料と年金額
20歳以上60歳未満の自営業者や学生、無職の方など、雇用されていない方が国民年金に加入します(国民年金第1号被保険者という)。10年以上加入して定額の保険料を納付すると、原則65歳から、保険料を納めた月数(加入月数)に比例した年金額がもらえます。最長で40年間(480ヶ月)加入することができ、その場合の年金額が満額(上限)となります。
保険料、および年金額の満額は、物価上昇率に応じて年度ごとに見直されます。参考までに、令和6年度の保険料は月額16,980円(年額203,760円)、年金額の満額は月額68,000円(年額816,000円)です。
付加年金
国民年金第1号被保険者については、保険料を納付する際に付加年金を申し込んで、毎月400円の保険料を上乗せすると、毎年の年金額に200円×付加保険料納付月数が上乗せされます。
例えば1年間で付加保険料を4,800円納付すると、毎年の年金額に2,400円が上乗せされます。すなわち、年金を2年受給すれば、付加保険料の元が取れることになります。最大40年で192,000円の付加保険料を納めれば、毎年の年金額に96,000円が上乗せされます。
ただし、付加年金は申し込んだ時点から保険料を納付することになるため、過去にさかのぼって付加年金を増やすことはできません。また、付加年金を申し込むと、原則として途中で中止することはできません。
国民年金第1号被保険者でも、国民年金基金に加入して年金額を上乗せする方は、付加年金を利用できません。厚生年金の被保険者(国民年金第2号被保険者)や、扶養する配偶者(国民年金第3号被保険者)も、間接的に国民年金に加入しますが、付加年金を利用できません。
保険料の免除制度、納付猶予制度
収入が減ったり、失業するなどして保険料を納付するのが困難な場合には、申請することで保険料の一部もしくは全部を免除したり、保険料の納付を猶予する制度があります。免除、猶予された期間も受給資格期間にカウントされ、10年以上で年金を受給する権利(年金受給権)を得ることができます。
ただし、保険料が免除された割合と期間によって年金額が減少しますが、全額免除の期間でも、保険料を納付したときの2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)が保障されます。なお、猶予の期間は受給額に反映されません。
同様に、20歳以上の学生で保険料を納付するのが困難な場合には、学生納付特例を申請することで納付が猶予されます。この場合も、受給資格期間にカウントされますが、受給額に反映されません。
これらの申請は、2年1ヶ月前まで遡って申請することができますが、それ以前の分は申請することができません。申請をしないで保険料を納めずにいると、万一の場合に受け取ることのできる障害年金や遺族年金が受け取れない可能性があります。年金は老後に受け取るだけのものではありませんので、注意してください。
他に、産前産後期間の原則4ヶ月間も、届け出により保険料の納付が免除されますが、この場合は全額納付したものと見なされ、年金額に反映されます。
保険料の追納制度
国民年金の保険料が、免除制度、納付猶予制度、学生納付特例によって免除や猶予された場合でも、10年以内であれば追納することができ、それによって年金額を増やすことができます。
任意加入制度
60歳で雇用先を定年退職して自営業や無職となった人で、学生の時に学生納付特例を申請しなかった人は、加入月数が480ヶ月に満たないため、満額の年金額をもらうことができません。このような場合、480ヶ月に達するか65歳を迎えるまで、国民年金に任意加入する(国民年金第1号被保険者になる)ことができます。任意加入して保険料を納付すれば、年金額を増やすことができます。また、任意加入中も付加保険料を納付することができます。
最後に
特に若い方は、年金なんて遠い先のことだと思って、制度内容を知らず、申請しないで過ごしてしまいがちです。しかし、過去にさかのぼって申請できないものもあり、年金を受け取る権利や、年金額を増やすチャンスを逃してしまうかもしれません。知らなくて損をすることはあっても、知っていて損はありません。複雑で分かりにくいところもありますが、自分の将来のお金にかかわる様々な制度に、ぜひ目を向けてみてください。
関連記事
「国民年金の任意加入」
(出典:「国民年金に加入の方(自営業・学生など)」(日本年金機構)(https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/kokunen/index.html)を元にライフプラン・シム作成)