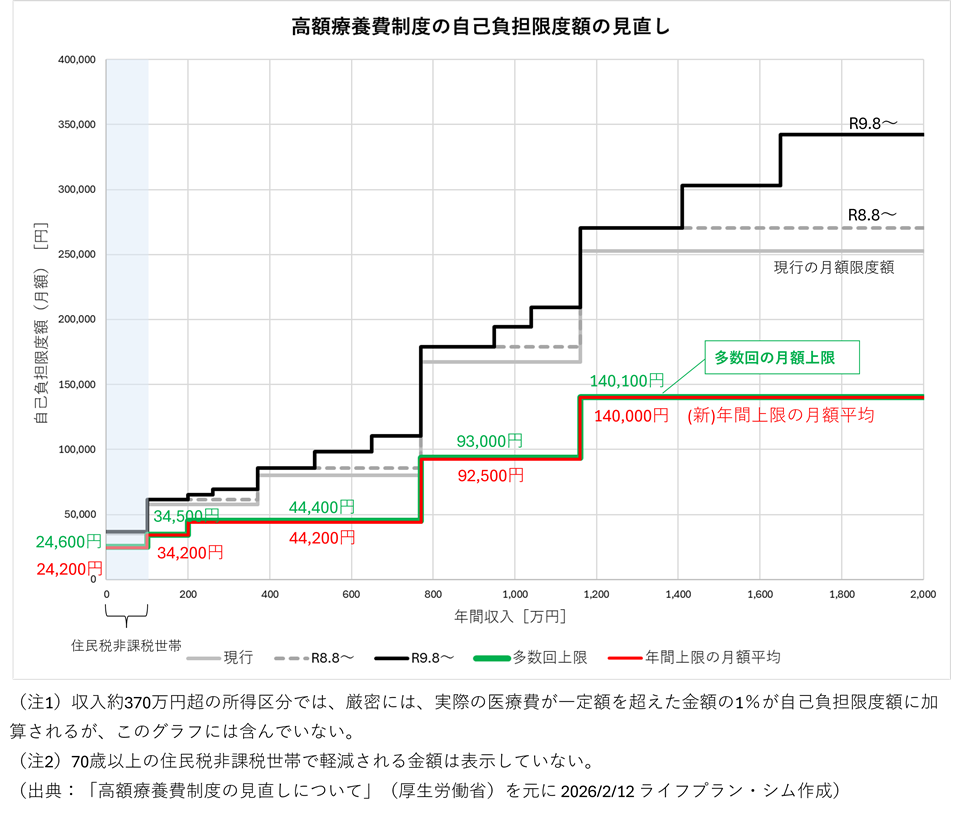所有者が不明の不動産が増加して社会問題になっていることから、2つの新しい制度が始まりました。令和6年4月1日から開始された不動産の相続登記の義務化と、令和5年4月27日から開始された相続土地国庫帰属制度です。特に、相続登記の義務化は、不動産を相続した方すべてに関係し、正当な理由がなく登記をしないと10万円以下の過料が科せられる可能性がありますので、よく理解しておく必要があります。
不動産の相続登記の義務化
対象は相続した不動産(土地、建物)で、2つのケースにより手続きが異なります。1つ目は、遺言で不動産を取得した相続人の場合で、取得したことを知ってから3年以内に、法務局にて相続登記(所有権移転登記)を行う必要があります。正当な理由がなく登記をしない場合には、過料が科せられる場合があります。
2つ目は、遺言がない場合で、相続人が相続したことを知ってから3年以内に、法務局にて相続登記もしくは相続人申告登記を行う必要があります。相続人による遺産分割協議などで、不動産を取得する人が決まった場合は、その人が相続登記を行います。しかし、遺産分割協議がまとまらない、あるいは争いが起きているなどの場合は、各相続人または複数人が連名でいったん相続人申告登記をすることで、時間的猶予が与えられます。その後、遺産分割協議がまとまった日から3年以内に相続登記をすれば、過料は免れます。
なお、1人で相続した場合は単独名義になりますが、複数人で相続した場合は共有名義になります。申請の手続きは、弁護士または司法書士に代行を依頼することもできます。単純な単独名義であれば、ご自分で手続することも難しくありません。登記には登録免許税(一定の要件を満たせば免税となる)、戸籍謄本などの必要な書類の取得にかかる費用、司法書士、弁護士に代行を依頼した場合はその費用がかかります。
また、注意が必要なのは、令和6年4月1日以前に相続した方も義務化の対象になることです。その場合は、制度開始日から3年以内の令和9年3月31日までに相続登記を行う必要があります。
相続土地国庫帰属制度
予期せず相続した土地などで、利用の予定が無く、負担が増していて手放したいと考えている土地の所有権を、国庫に帰属させることができる制度です。その土地が、通常の管理や処分をするよりも、多くの費用や労力がかかる土地ではないことが要件であり、一律の審査手数料と、算出された10年分の標準的な負担金(管理費用)を納付する必要があります。負担金は、おおむね面積によらず20万円ですが、市街化区域内の宅地、農地や、管理に費用がかかる森林などは面積に応じて算出されます。
なお、土地の単独所有者だけでなく、共有持分の共有者全員で共同申請することも可能です。また、制度開始前に取得した土地も対象です。
具体的に引き取ることができない土地とは、以下の通りです。
(1) 申請することができない土地
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権※1が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌が汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲について争いがある土地
※1 使用収益権:地上権、賃借権など
(2) 承認を受けることができない土地
A 一定の勾配、高さの崖※2があって、管理に過分な費用、労力がかかる土地
B 土地の管理、処分を阻害する有体物※3が地上にある土地
C 土地の管理、処分のために、除去しなければならない有体物※4が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との訴訟によらなければ管理、処分ができない土地
E その他、通常の管理、処分に当たって過分な費用、労力がかかる土地
※2 崖:勾配30度以上+高さ5メートル以上
※3 地上の有体物:工作物、車両又は樹木その他(通常の管理、処分可能な柵や森林などは除く)
※4 地下の有体物:産業廃棄物、建築資材、建物の基礎、水道管、浄化槽、井戸、大きな石など
(出典:「相続登記の申請義務化特設ページ」(法務省)(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00590.html)、
「相続土地国庫帰属制度について」(法務省)(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html)を元に、ライフプラン・シム作成)