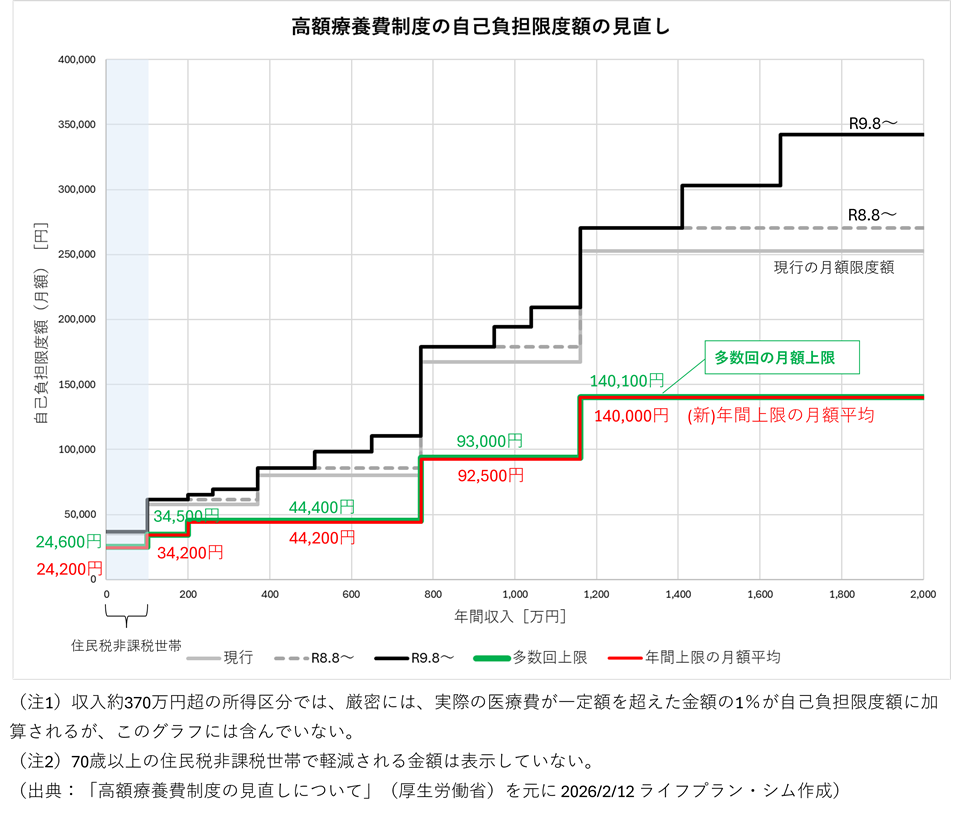グラフには、後期高齢者医療制度の保険料に関する3つの全国平均値の推移を示しています。1つ目は、収入に寄らず誰にもかかる均等割額の年額で、2つ目は所得に応じて徴収される所得割の保険料率、3つ目は全国平均保険料の年額です。2008年(平成20年)から制度化された後期高齢者医療制度ですが、都道府県ごとに均等割額、保険料率が定められ、2年に一度改定されます。
グラフにおいて、2018年度には保険料率が若干下がっていますが、それを除けば、後期高齢者の増加に伴って数値は増加し続けており、平均保険料は2008年比で約25%増加しています。なお、平均保険料は均等割額との積み上げグラフで表しており、2022年で均等割額が47,777円で、平均保険料は77,663円となっています。また、保険料率のみ右軸の目盛りを参照してください。参考までに、国民健康保険の全国平均保険料(介護保険料は除く)は2021年時点で91,310円となっています。
それでも、1割~3割の窓口(本人)負担を除いた残りの50%を公費(国と地方自治体)で負担し、40%を75歳未満の医療保険で支え、残りの10%を後期高齢者医療制度の保険料で賄っている状況を理解すれば、保険料の上昇もある程度やむを得ないと感じざるを得ません。一方で、現実に負担する側にとっては、保険料の値上りは厳しいのも事実です。
また、保険料の計算においては、所得割の計算のもととなる賦課所得は、国民健康保険と同様、前年の所得から住民税の基礎控除額(高額所得者を除き43万円)を差し引いた金額となります。また、均等割額と所得割額を合計した額には、賦課限度額すなわち保険料の上限額が設定されています。2022年の賦課限度額は66万円で、収入金額ベースでは1,000万円前後になります。
この賦課限度額も、2008年当初は50万円でしたが、2012年に55万円、2014年に57万円、2018年に62万円、2020年に64万円と引き上げられてきました。そして、2023年(令和5年)の厚生労働省の医療保険制度改革において、出産一時金を42万円から50万円に引き上げるにあたり、後期高齢者医療制度の保険料からも一部を支援する方針が示され、2024年から73万円、2025年からは80万円に、段階的に引き上げられる見通しです。
なお、2024年からの均等割額も50,500円程度に、保険料率も10.7%程度に、平均保険料も87,200円程度になる見通しで、ますます保険料が上がりそうです。ただし、後期高齢者医療制度でも国民健康保険制度と同様に、住民税非課税世帯やこれに準じる世帯に属する被保険者には、世帯所得に応じて均等割額の7割、5割、2割が軽減されたり、本人の賦課所得により、所得割額の50%、25%が軽減される措置がありますので、該当の可能性がある方はご確認ください。
特に均等割については、本人の賦課所得ではなく、本人が属する世帯の所得(世帯内の後期高齢者の被保険者全員と世帯主の総所得の合計)で判定されますので、親子同居世帯などは注意が必要です。かといって、安易に世帯分離を行うと、世帯主側の扶養控除が受けられなくなるケースなどもありますので、メリット、デメリットをよくお調べください。
(出典:「医療保険制度改革について」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001037866.pdf)を元にライフプラン・シム作成)