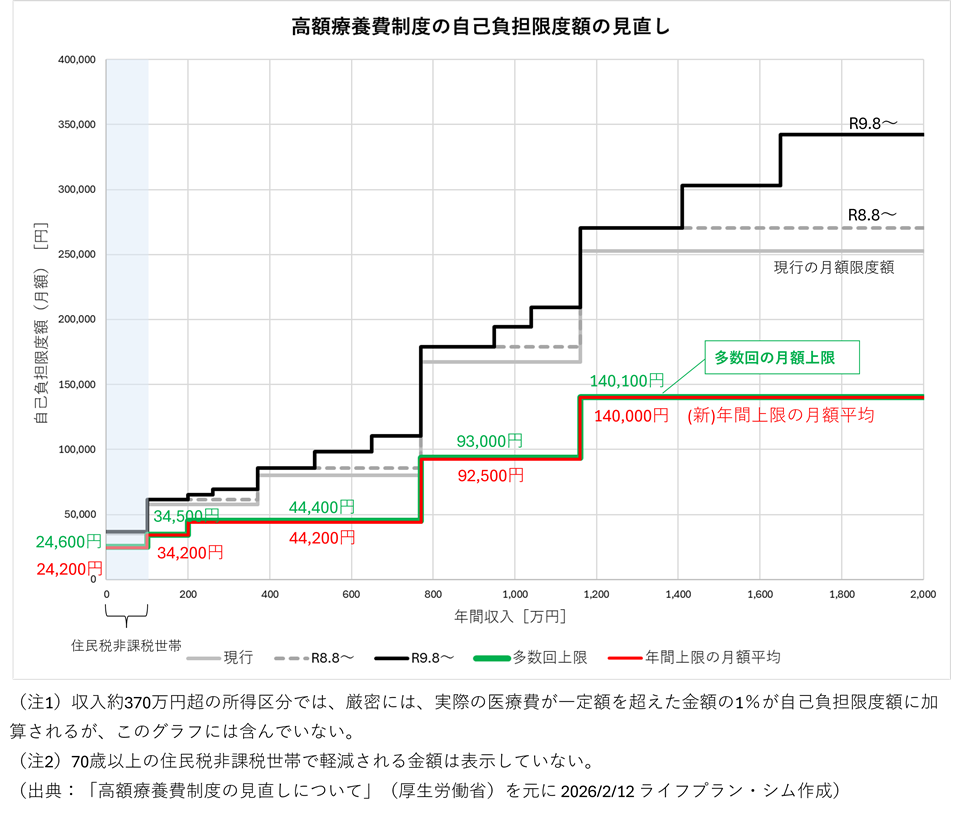生命保険や医療保険、個人年金保険に加入して保険料を支払っている場合、所得税の課税所得を計算する際に、保険料の全額または一定の割合を課税所得から差し引く(控除する)ことができ、それによって所得税を軽減する生命保険料控除の税制があります。給与所得者でこれらの保険料を給与天引きにしている方は、年末調整の際に給与天引きの保険料については自動的に、そうでないものも申告すれば年末調整で納税額が調整され、確定申告せずに保険料が控除されます。一方、自営業者や年金所得者は確定申告が必要になりますし、申告漏れがあった給与所得者も確定申告すれば還付が受けられますので、年末を前に生命保険料控除について整理しておきましょう。なお、保険期間や受取人などによって控除の対象とならないものがありますので、詳しくは国税庁のホームページでご確認ください。
まず、平成22年に税制改正がなされたことにより、保険契約の締結日が平成23年12月31日以前と、平成24年1月1日以降で保険料控除の扱いが異なります。平成23年までに締結した保険は、一般生命保険と個人年金保険の2つに区分され、それぞれ最高5万円までの控除で、合計で最高10万円までの控除が受けられました。しかし、平成24年以降に締結の保険では、一般生命保険が一般生命保険と介護医療保険に分割され、それぞれ4万円までの控除が受けられるようになりました。また、これに合わせて個人年金保険の控除も上限が4万円に改正になり、3つの区分の合計で最高12万円までの控除が受けられるようになりました。
なお、保険料と控除額の関係は、単純に上限額まで保険料の全額が控除される訳ではなく、グラフに示すように、第一の一定額までは全額控除されるも、これを超過すると第二の一定額までは超過した保険料の半分が控除に加算され、さらに第二の一定額を超過すると上限額に達するまで、超過した保険料の1/4が控除に加算されます。また、新制度と旧制度の保険の両方に加入する場合には注意が必要です。①旧制度の保険料が6万円を超過する場合は、旧制度での保険料控除の計算を行った上で最高5万円までの控除を受けることができますが、②旧制度の保険料が6万円以下の場合は、新制度と旧制度それぞれの控除額の計算を行って合計した金額の上限が4万円に制限されます。これは、旧制度で6万円の保険料の場合、4万円の控除額となりますので、これが新制度での上限額に達するという意味です。そして、旧制度の控除額だけで4万円の上限を超える場合は、旧制度の計算のみを使用して5万円を上限にすることができるということになります。なお、いずれの場合も、全ての区分の控除額の合計は最高12万円に制限されます。
これらの計算の仕方は分かりにくいですが、インターネットを利用したe-taxでの確定申告を行うと、新契約、旧契約の年間保険料を入力するだけで自動で控除額を計算してくれますので、e-taxによる確定申告をお勧めします。10月以降くらいから、契約の保険会社から保険料控除証明書が送られてきますので、それを集めておいて、保険の区分と保険料をe-taxに入力して行くだけです。控除証明書を電子データで受取ることもできます。なお、e-taxで確定申告書や確証などの電子データをインターネットで送信する場合には電子証明書(マイナンバーカードなど)などが必要になります。電子データの送信ではなく印刷して税務署に郵送することもでき、その場合、電子証明書は不要です。
また、定期的に支払う保険料を一定年数分まとめて前納した場合などは、保険会社が前納保険料を一旦預かって、納付期間中はそこから毎年納めていることになりますので、その間保険料控除を毎年受けることができます。保険会社から毎年1年分の保険料に相当する保険料控除証明書が送られてきますので、忘れずに申告してください。一方、保険料が一括払いの終身保険や年金保険などの場合は、その年だけの保険料控除になります。
年末調整や確定申告で生命保険料控除を行うと、翌年の住民税でも生命保険料が控除されます。住民税は、確定申告や年末調整の結果を受けて、自治体が計算して徴収します。ただし、所得税と住民税では保険料の控除額が異なり、新制度での控除額は区分毎に最高2万8千円、旧制度での控除額は最高3万5千円、全ての区分の合計では最高7万円に制限されます。
なお、令和4年度の税制改正要望では、所得税における生命保険料控除の上限を12万円から15万円(保険区分毎の上限を5万円)に引き上げる要望が出されており、実現されると多少なりとも減税になる方も多いと思います。
(出典:「生命保険料控除」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm)を元にライフプラン・シム作成)