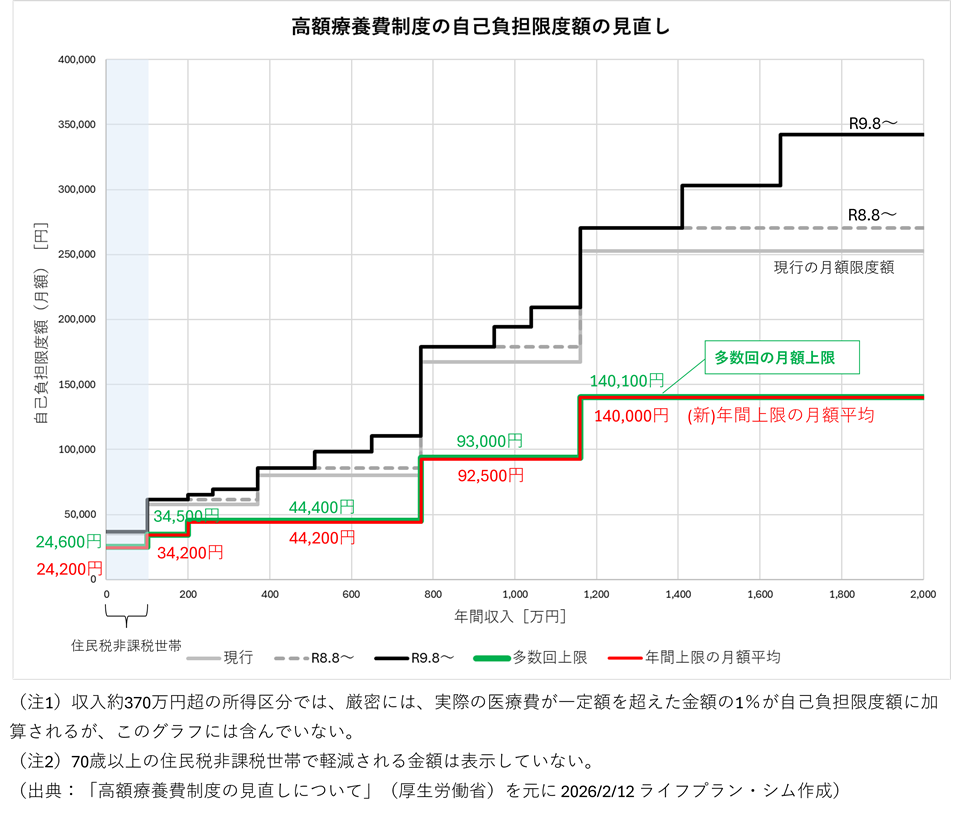年金の構成
公的年金には、原則20歳以上~60歳未満の全ての人が加入する国民年金と、70歳未満の会社員・公務員が加入する厚生年金があります。
国民年金は、40年(480ヶ月)の加入を上限として保険料は定額で、年金受給額も40年加入での満額を基準として、加入月数にのみ比例します。ただし、保険料、年金受給額の満額は、年度毎に物価や賃金の変動を反映して見直されます。
一方、厚生年金の保険料は、給与収入(標準報酬月額)に対して定率の金額で、これを労使折半で負担します。厚生年金に加入すると、年齢にかかわらず同時に国民年金にも加入することになりますが、国民年金の保険料もこれに含まれます。厚生年金の年金受給額は、国民年金に相当する基礎年金部分(満額が上限)と、厚生年金に加入している期間の平均標準報酬月額に比例した報酬比例部分を合算した額となります。
年金受給額の概算を求める計算式
(1) 国民年金(基礎年金部分)の受給額(年額)
国民年金受給額満額×国民年金加入月数/480ヶ月
([注] 国民年金受給額満額は毎年度見直されるものです。将来にわたって、この計算結果の受給額が保証されるものではありません。また、保険料の一部あるいは全部を免除された加入期間がある場合は、免除額やその期間に応じて受給額が減額されます。)
令和6年度の国民年金の受給額満額は、物価上昇を反映して令和5年度から2.7%引上げられ、816,000円です。なお、昭和31年4月1日以前の生まれの方は、813,696円です。年度ごとの満額は、厚生労働省、日本年金機構のホームページや、各自治体のホームページで確認できます。概算を求める場合は、約80万円としてもよいでしょう。
また、就職以前(20歳以上の学生の時)に国民年金に加入して保険料を納付していた場合は、国民年金の加入月数にこの期間も含めてください。60歳以降に任意加入する場合は、その期間も含めてください。ただし、トータル480ヶ月を超えて加入することはできません。
なお、付加保険料を収めることで上乗せされる付加年金は、計算に含んでおりません。
【計算例】国民年金加入期間38年(456ヶ月)の場合
81.6万円×456ヶ月/480ヶ月=77.52万円
(2) 厚生年金(報酬比例部分)の受給額(年額)
厚生年金加入期間の平均年収/12ヶ月×0.55%×厚生年金加入月数
([注] 本計算式は、あくまでも簡易的に受給額を求めることを目的としており、結果は概算を示すものです。また、将来の加入期間を含む場合、平均年収も加入月数も増減する可能性があるため、将来にわたって、この計算結果の受給額が保証されるものではありません。)
就職から退職するまでの全期間の平均年収(賞与を含む)を求める必要があります。将来分を含めた平均年収が分からない方は、一般的に38歳の年収額に一致しますので、その金額が分かればそれを用いてください。
実際の計算には、毎年の標準報酬月額が用いられ、過去の賃金を現在価値に換算する再評価率が掛けられます。年収がおよそ2,000万円以上の期間を含むケースや、賞与の比率が極端に高いケースなどは、平均年収を用いた簡易的な式では、実際と大きなずれが生じる可能性があります。
なお、家族構成によっては、一定期間、加給年金を受給できる場合などがありますが、ここでは加給年金などの付加的な年金は一切含んでおりません。
【計算例】厚生年金加入期間38年(456ヶ月)、38歳の年収600万円の場合
600万円/12ヶ月×0.55%×456ヶ月=125.4万円(報酬比例部分)
基礎年金部分+報酬比例部分=77.52万円+125.4万円=202.92万円
年収の壁を超える場合や雇用延長で年金がどれだけもらえるか
年収の壁を越えて社会保険料を負担しながら働く場合や、定年退職後に雇用延長などで働く場合、厚生年金がいくらもらえるかの計算も、上記の計算式で求められます。どちらの場合でも、加入月数とその期間の平均年収が分かれば年金受給額が計算でき、他の加入期間から求めた受給額と合算することができます。ただし、厚生年金の基礎年金部分のトータル加入月数は480ヶ月が上限で、受給額も満額が上限となります。
【計算例】年収300万円で5年間(60ヶ月)雇用延長した場合
基礎年金部分=81.6万円×(480ヶ月-456ヶ月)/480ヶ月=81.6万円×24/480=4.08万円
報酬比例部分=300万円/12ヶ月×0.55%×60ヶ月=8.25万円
年金受給額=(77.52万円+4.08万円)+(125.4万円+8.25万円)=81.6万円+133.65万円=215.25万円
関連記事
「年金受給額の推移とインフレ下で低下する将来価値(将来の年金受給額)」
「加給年金」
「国民年金の任意加入」
「厚生年金の加入期間」
もっと詳しい年金シミュレーション
①当サイトの「ライフプランシミュレーション」
無料の会員登録をして、年齢、現在の年収、退職年齢、家族構成などを入力すれば、加給年金を含めた年金受給額の概算が求められます。
②「厚労省公的年金シミュレーター」 https://www.mhlw.go.jp/stf/kouteki_nenkin_simulator.html
登録など不要で、年齢と現在の年収(990万円以下)を入力すれば、年金受給額の概算が求められます。
③「ねんきんネット」 https://www.nenkin.go.jp/n_net/
マイナンバーカードもしくは基礎年金番号を使ってアカウント登録すれば、あなたの年金受給額を試算できます。
(出典:「[年金制度の仕組みと考え方]第3 公的年金制度の体系(年金給付)」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/nenkin_shikumi_003.html)を元にライフプラン・シム作成)