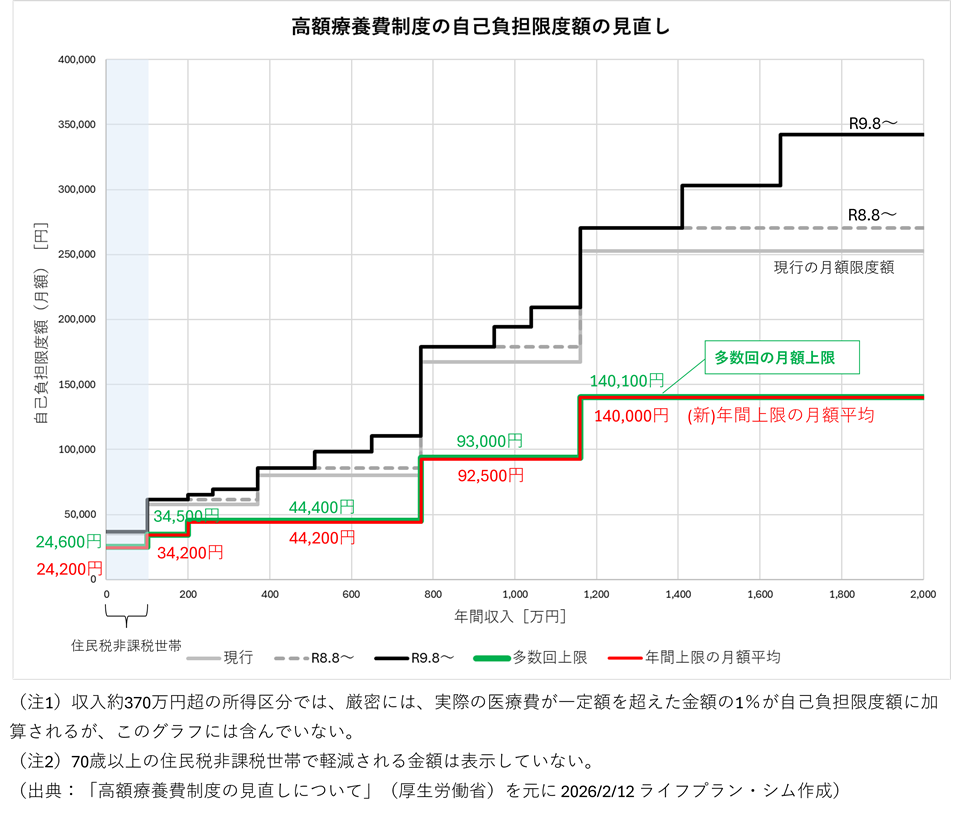年収の壁には、税金の壁(100万円、103万円)、社会保険料の壁(106万円、130万円)、配偶者控除の壁(150万円、202万円)があります。これらの詳細は、記事「配偶者の年収の壁」 をお読みください。このうち「103万円の壁」、すなわち所得税の税金の壁が改正になり、令和7年の年末調整や確定申告、令和8年の源泉徴収から適用になります。
具体的には、給与収入者の低所得者層では「103万円の壁」が「160万円の壁」に引上げられます。その内訳は、①基礎控除額の10万円引上げ、②低所得者層の基礎控除額の37万円上乗せ、③中所得者層の基礎控除額の上乗せ特例、④給与所得控除の最低保障額の10万円引上げ、となっています。それぞれ、詳しく見ていきましょう。
①基礎控除額の10万円引上げ(恒久的措置)
所得税の計算において、収入がある全ての方の所得から非課税枠である「基礎控除」が差し引かれます。過去を振り返ると、約30年前から基礎控除額は38万円に添え置かれてきました。
働き方改革推進による平成30年の改正(令和2年から適用)で、給与所得控除額、公的年金控除額を10万円引き下げる代わりに、基礎控除額が38万円から48万円に見直されましたが、これは単なる振替にすぎません。
また、同年の改正で所得制限が設けられ、所得が2,400万円以下の方は48万円、2,400万円超では32万円、2,450万円超では16万円に逓減され、2,500万円超では基礎控除は受けられなくなりました。
しかし、昨今の物価上昇や最低賃金の引上げトレンドにより、基礎控除額を引上げるべきとの気運が高まり、令和7年度の税制改正で、30年間の物価上昇率を勘案して20%の引上げ、金額ベースで+10万円の58万円に引上げられました。これは、所得が2,350万円以下の方への適用で、2,350万円超の方に変更はありません。つまり、2,350万円超の方は48万円、2,400万円超の方は前述のとおり逓減されます。
なお、今後の物価上昇により、基礎控除をどのように見直すかは引き続き検討されています。
②低所得者層の基礎控除額の37万円上乗せ(恒久的措置)
所得税が非課税となる年収の壁が、主婦や学生がパート・アルバイトなどで働く機会を制限していることや、生活保護の所得水準、最低賃金の水準とのバランスが取れていないなどの意見から、低所得者層の基礎控除額に37万円を恒久的に上乗せする措置が取られました。
所得制限としては所得132万円以下の方のみに限られ、給与収入のみの方では収入200万3,999円以下、年金収入のみの65歳以上の方では収入242万円以下の場合に、基礎控除額が95万円に引上げられます。なお、この上乗せ加算は、居住者(国内に生活の本拠となる住所があるか、現在まで引き続き1年以上居所がある者)のみに適用されます。
③中所得者層の基礎控除額の上乗せ特例(令和7・8年の時限措置)
賃金上昇が物価上昇に追いついていないことへの対応で、令和7年、8年の時限的な措置として中所得者層の基礎控除額に、所得に応じた上乗せが行われます。
具体的には表に示すように、所得336万円以下に対して基礎控除額が88万円(30万円の上乗せ)、所得489万円以下に対して68万円(10万円の上乗せ)、所得655万円以下に対して63万円(5万円の上乗せ)となっています。所得655万円超への上乗せはありません。それぞれの所得に相当する給与収入金額は表をご覧ください。なお、この上乗せ加算は②と同様に、居住者のみに適用されます。
これまでと比較して、①③による所得控除額は、所得に応じて40万円~15万円の引上げになり、税額ベースでは2万円~4万円の税負担軽減になります。
④給与所得控除の最低保障額の10万円引上げ
最後は、給与所得控除額の最低保障額の引上げです。前述のように、令和2年から基礎控除額と振替で給与所得控除額が10万円引き下げられ、最低保障額は55万円となっていました。②と合わせた低所得者層への非課税枠の拡大の観点から、給与収入190万円以下の給与所得控除が65万円に引上げられました。給与収入190万円超では変更はありません。
なお、②と④を合わせて、給与収入が約200万円以下の方の基礎控除額が95万円+給与所得控除額が65万円となり、合わせて160万円までは所得税が非課税となります。これで、「103万円の壁」が「160万円の壁」に引上げられることになります。
また、①と④を合わせて、扶養控除の収入要件が「103万円の壁」から「123万円の壁」に引上げられます。19~22歳の扶養親族には、新たに特定親族特別控除が設けられ、①④を含めて150万円以上に引上げられます。配偶者特別控除は④により、下限では10万円引上げられ「160万円の壁」となりますが、上限の「202万円の壁」は据え置かれます。
その他の年収の壁
今回の令和7年度の税制改正では、住民税の基礎控除額については、地方自治体の財政の状況から据え置きとなっており、もうひとつの税金の壁である「100万円の壁」は給与所得控除の引き上げ分だけ上昇して「110万円の壁」となります。
また、社会保険料の壁では、厚生年金や健康保険への加入要件を見直して拡大し、社会保険料の壁を将来的に撤廃する方向で議論が進められています。同様に、配偶者控除の壁についても、夫婦共働き世帯の増加などにより、廃止について議論が進められています。
(出典:「令和7年度税制改正による 所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf)を元にライフプラン・シム作成)