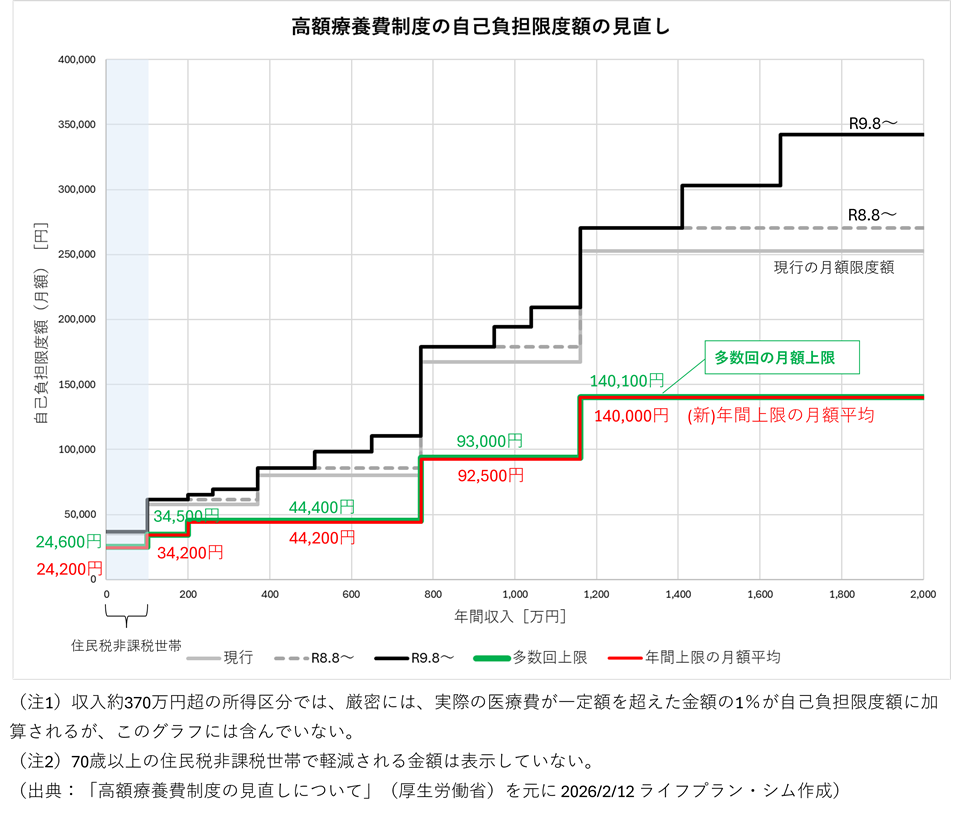これまで、タワーマンションの上層階では、市場価格と比較して相続税評価額が割安になることから、富裕層が相続税対策としてタワーマンションの一室を購入するケースが多々ありました。これは、マンションなどの区分所有不動産では、土地を共有持分の割合(床面積の割合)で分割利用していると見なされることから、戸数が多いほどその面積が小さくなることと、建物の相続税評価額(固定資産税評価額)には、階の上下による差がないことによりました。
この対策として、令和6年1月1日以降に発生する相続、遺贈については、相続税評価額の計算ルールが大きく見直されます。その影響は、築年数が浅く、戸数が多く、高層マンションの上層階ほど大きくなり、一般的な中層のマンションでも、従来の相続税評価額の1.5倍前後になりますので、この機会に確認することをお勧めします。
マンションなどの区分所有不動産については、
相続税評価額=区分所有権(家屋)の価額+敷地利用権(土地)の価額
で評価され、
区分所有権の価額=家屋の固定資産税評価額、
敷地利用権の価額=路線価×地積×敷地権の割合(共有持分の割合)
で求められました。しかし、今回の改正では新たに「区分所有補正率」が定義され、従来の相続税評価額に区分所有補正率が掛けられることになりました。つまり、
相続税評価額=(区分所有権の価額+敷地利用権の価額)×区分所有補正率
となります。
この区分所有補正率を求めるにあたって、まず「評価乖離率」を求めます。評価乖離率は以下の式で定義されます。
評価乖離率=3.220-0.033×築年数+0.239×総階数/33+0.018×所在階数-1.195×敷地利用権の面積/専有部分の床面積
注1)築年数は、一棟の区分所有建物の築年数(1年未満は1年とする)
注2)総階数には地階を含まない、33を超える場合は33とする
注3)所在階数が複数に跨る場合は低い方の階数、地階はゼロ階とする
注4)評価乖離率がゼロまたは負の場合は、評価額をゼロとする
評価乖離率は、市場価格と比較して評価額がどれだけ割安になっているか(乖離しているか)を示す率で、統計的に求められた計算式です。築年数が浅いほど、建物の階数が高いほど、所在階が上階であるほど、戸数が多いほど乖離率は大きくなります。
そして、この評価乖離率の逆数(=相続税評価額/市場価格)を評価水準とし、評価水準が60%未満の場合には、評価額が市場価格の60%となるように補正し、100%を超える場合には100%となるように補正します。これが区分所有補正率で、以下のようになります。
評価水準の範囲 区分所有補正率
------------------------------------------------
評価水準< 60% 評価乖離率×0.6
60%≦評価水準≦100% 1(補正無し)
100%<評価水準 評価乖離率
(注)一棟の区分所有建物のすべての専有部分、および敷地を単独で所有する場合、敷地利用権の区分所有補正率は1を下限とする
なお、区分所有補正率については、以下の場合には適用されません。
・事業用のテナント物件など、構造上、居住用とできないもの
・一棟所有の賃貸マンションなど、登記上の区分建物でないもの
・地階を除く総階数が2以下のもの
・二世帯住宅など、親族と区分所有する居住用のもの
・借地権付き分譲マンションの敷地である貸宅地(底地)を評価する場合
実際に計算してみたい場合は、国税庁のホームページ「居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書」(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/1470-17.htm)から、エクセルの計算ツールがダウンロードできますので、活用されるとよいでしょう。
一例ですが、築年数=10年、総階数=14階、所在階数=7階、敷地利用権の面積/専有部分の面積=0.5とすると、
評価乖離率=3.220-0.330+0.101+0.126-0.598=2.519
区分所有補正率=2.519×0.6=1.5114
となります。つまり、従来の相続税評価額の約1.5倍となります。
なお、小規模宅地等の特例が適用可能な条件であれば、補正後の敷地利用権の価額が80%減額されます。
(出典:「『居住用の区分所有財産』の評価が変わりました」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023011-040_01.pdf)、
「マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議について」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/0023006-018.pdf)
を元に、ライフプラン・シム作成)