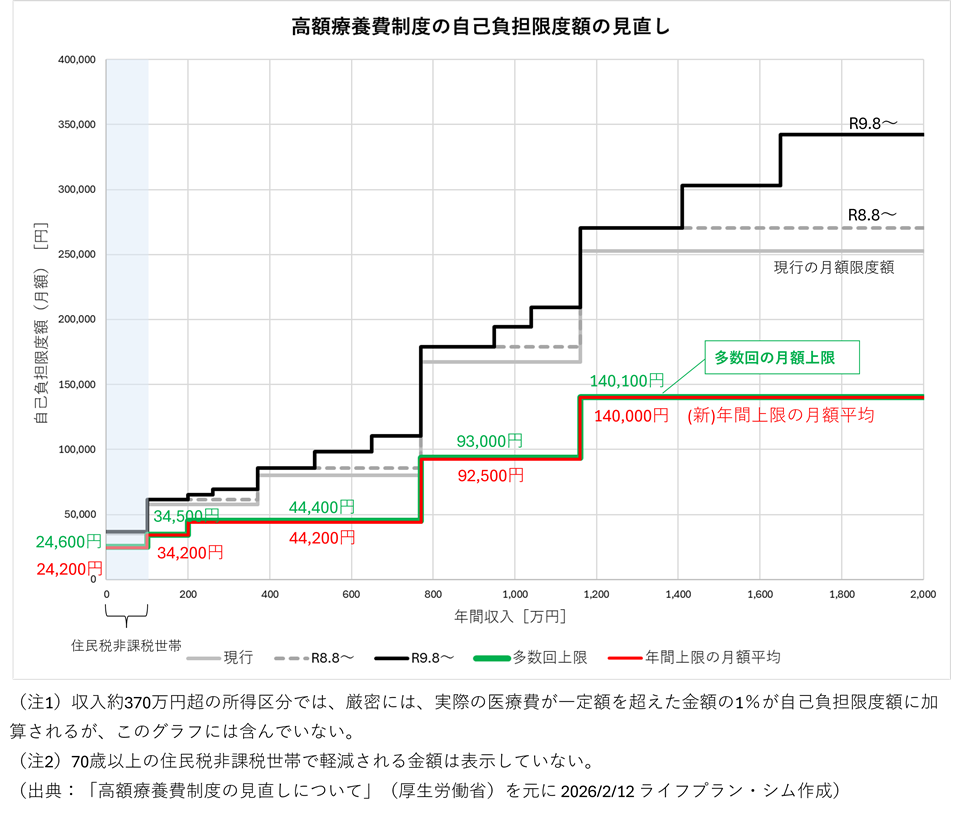住宅をリフォームする際に、少しでも負担を軽くしたいと考えると思いますが、税制面で大きく2つの特別減税制度があります。ひとつは、リフォーム促進税制(住宅特定改修特別税額控除)で令和5年12月末までの時限措置、もうひとつは住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)で令和7年12月末までの時限措置です。リフォーム促進税制は、住宅ローン利用の有無に関係なく、要件を満たせば申請できます。なお、これらの控除を受けるためには、建築士等が発行した増改築等工事証明書などを用意する必要があります。
1. リフォーム促進税制
リフォーム促進税制の対象となるリフォーム内容には、耐震化、バリアフリー化、省エネ化、同居対応、長期優良住宅化があり、それと併せて実施されるその他の改修が対象となります。改修工事が完了して居住を開始した年の所得税、改修工事が完了した翌年の固定資産税のそれぞれ一部が控除される制度です。ただし、耐震化のみ、居住開始の要件は除外されている一方、同居対応は固定資産税控除の対象外です。また、自己が所有する居住用家屋で(耐震化は除く)、工事後の床面積が50m2以上、かつ1/2以上が自己の居住用であること、控除を受ける年の所得が3,000万円以下であること、などの要件を満たす必要があります。
所得税の控除としては、2段階の控除率が設けられており、1段階目は、メインのリフォーム対象工事費の10%に相当する額が所得税から税額控除されます。ただし、対象工事費は実際にかかった費用ではなく、国が定めた標準工事費が適用され、他に補助金を受け取る場合は補助金を差し引いた費用になります。また、対象工事費のうち控除される上限がリフォーム内容に応じて定められており、200万円、もしくは250万円となっています。また、耐震化を除き、50万円以上の工事が対象となります。
2段階目は、メインの対象工事で控除上限を超過した分と、同時に行うその他の改修工事について、工事費の5%相当分が減税になります。このとき、その他の改修工事費は、対象工事費と同額まで(ただし、控除上限まで)、かつ、対象工事費と合わせた総工事費1,000万円までが対象となります。また、耐震化、バリアフリー化、省エネ化、同居対応のリフォームは併用することが可能です。さらに、省エネ化と併せて、太陽光発電設備を設置する工事を行う場合は、対象工事費の上限が100万円増額されます。
固定資産税の控除としては、同居対応は対象外ですが、耐震化が1/2、バリアフリー化、省エネ化がそれぞれ1/3、長期優良住宅化が2/3を控除され、バリアフリー化、省エネ化は併用が可能です。なお、控除される家屋面積に上限があり、バリアフリー化が100m2まで、それ以外が120m2までとなっています。
2. 住宅ローン減税制度
リフォームの工事費に、返済期間10年以上の住宅ローンを利用する場合で、改修工事費が100万円以上の場合には、住宅ローン残高2,000万円を上限として住宅ローン控除が受けられます。年末の住宅ローン残高の0.7%相当を所得税から控除でき、最大10年間控除できます。リフォーム促進税制の耐震化の控除と、住宅ローン控除は併用することができますが、それ以外のリフォーム内容では併用できません。
なお、リフォーム促進税制との要件の違いは、控除を受ける年の所得が2,000万円以下であること、対象に増築、改築(取り壊して既存と同じ規模の家屋を建てる)および、壁、床、階段、屋根などの過半以上の修繕または模様替え、一定規模(一室の床または壁の全部など)以上の修繕または模様替えなどが含まれ、対象範囲が広いことです。
リフォーム促進税制の対象となっている省エネ化や耐久化(長寿命化)に関するリフォームについては、国や地方自治体による補助金もありますが、施工業者が申請を行うなど手続きが異なったり、適用条件もあります。無理して想定を超える費用になることなどが無いように、事前によく確認しておくとよいでしょう。
(出典:「住宅のリフォームに利用可能な税制特例」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000011.html)を元に、ライフプラン・シム作成)