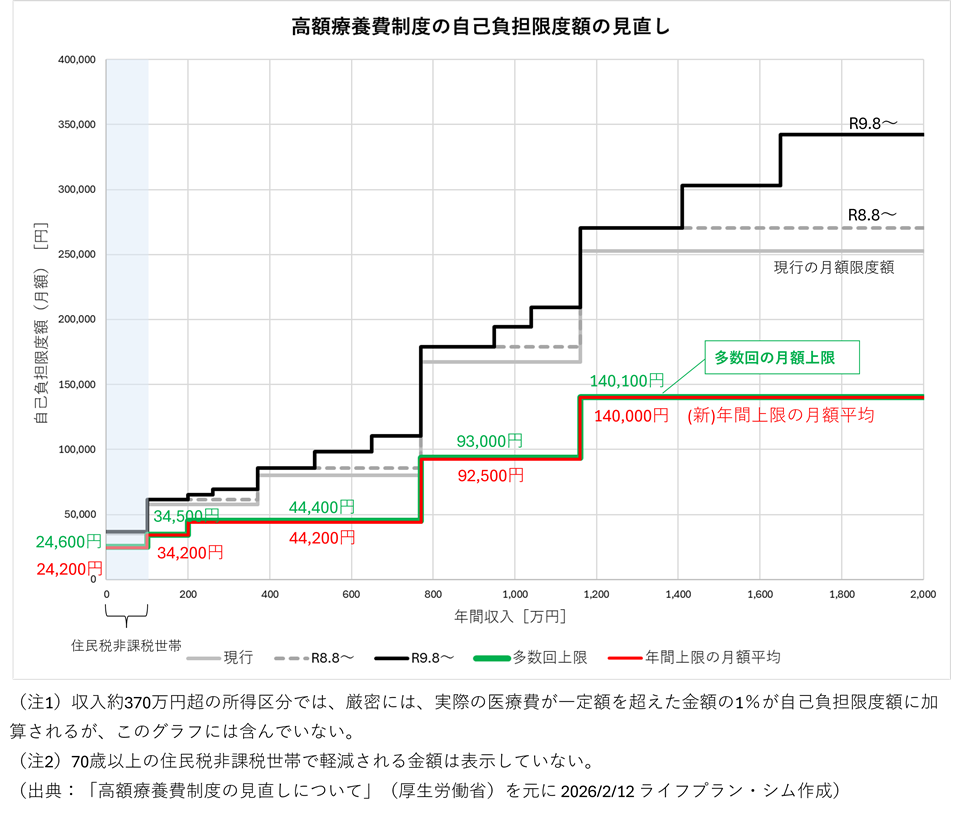国税庁によると、令和3年の被相続人の数(死亡者数)は約150万人、そのうちの9.3%において相続税の申告がなされ、納税した相続人は約30万人とのことです。相続財産が一定以上ある場合には、10ヶ月以内に相続税の申告を終えて、相続税を納めなければなりません。ここでは、そんな時に備えて相続税の課税遺産総額(課税対象額)の求め方と、それを踏まえてどのような節税の方法があるかを簡単に説明します。親の相続のみならず、自分の死後に配偶者や子どもが相続する場合に、財産をどう残すかを考えるきっかけになれば幸いです。
(1)法定相続人の定義
まず、課税遺産総額の計算に大きくかかわる、法定相続人について整理しておきます。遺言や遺産分割協議などにより、実際に相続する人と法定相続人が必ずしも一致しない場合もありますが、法定相続人は法的に相続が認められた人で、その人数は、ここでは相続税を計算する上で用いられる数と認識しておいてください。
法定相続人は、相続の優先順位によって決定されます。配偶者は常に相続人であり、それに加えて、①子、②直系尊属(父母、直系の血族)、③兄弟姉妹、の優先順位で、順位が上位の相続人がいない場合に次の順位が相続人となります。ただし、①③で子、兄弟姉妹が死亡などで相続時にいない場合には、孫(死亡などで相続時にいない場合はさらにその子孫)、甥、姪が代襲相続します。また、②で父母が死亡などで相続時にいない場合に限り、祖父母(さらにその直系の父母・・)が法定相続人となります。
なお、非行などにより、民法上の相続の資格を欠格した相続人と、被相続人が予め家庭裁判所に排除の請求をした相続人は、法定相続人にカウントしませんが、欠格、排除された相続人に子がいる場合は代襲相続人としてカウントされます。逆に、相続を放棄した相続人は、放棄が無かったものとカウントされますが、代襲相続はありません。胎児や非嫡出子(婚姻外の子)も相続の権利を有し、カウントされます。また、養子も実子と同等の権利を有しますが、法定相続人としては、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までカウントされます。その他の例についてはここでは割愛します。
(2)相続財産への加算対象と減算対象
相続財産の対象としては、被相続人が相続時点で所有していた、金銭に見積もることのできる全ての財産と、死亡により相続人が受け取ることのできる死亡保険金、死亡退職金などがありますが、相続時清算課税による贈与があった財産についても相続財産とみなされます。また、相続開始前3年以内に行われた贈与についても同様で、どちらも贈与時点での価格(評価額)が加算され、納税済みの贈与税があれば、相続税から控除、還付されます。
一方、相続財産から減らせるものとして、債務と葬儀費用があります。債務については、借入金や未払金の金額を、債務を相続する人の相続財産から減算することができます。もし、相続財産を合計して債務超過が確定しているのであれば、相続放棄をすることができ、債務超過が懸念される場合には、相続人全員一致の選択として、相続財産の範囲で債務を弁済する限定承認を選ぶこともできます。なお、相続放棄、限定承認は、相続から3ヶ月以内に家庭裁判所へ届け出る必要があります。
(3)死亡保険金控除、死亡退職金控除
相続税には、遺族の生活を一定程度保障するための非課税控除があります。死亡保険金と死亡退職金にはこの控除があり、法定相続人の数をn人とすると、それぞれから最大で500万円×nを控除することができます。死亡保険金の受取人が複数の場合は、死亡保険金額の比率で控除を按分します。死亡退職金も同様です。
なお、死亡保険金、死亡退職金は、遺言で受遺者(遺産を受け取る人)を指定していなくても、保険契約や雇用契約などで指定された受取人に全額を相続することができ、遺言の代わりにもなります。したがって、遺産分割協議の対象ではない相続財産ということになり、みなし相続財産と呼ばれます。それぞれの相続人が受け取る死亡保険金、死亡退職金から、按分した控除をそれぞれ差し引いて残った額を課税価格と言い、相続人ごとの課税価格の合計が、相続税を求める基礎となります。
(4)相続税評価額と特例
(3)の控除以外で課税価格を時価よりも減らせるものとしては、不動産の相続税評価額があります。土地については、相続税評価額が公示価格(取引の指標)の80%を目安に定められています。また、家屋を建てて賃貸をしている土地(貸家建付地)では、自用地評価額から賃貸部分の評価額を減らすことができます。この評価減は、借地権割合(貸家が建つ土地の割合)×借家権割合(一律30%)×賃貸割合(課税時期に賃貸されている床面積の割合)になります。建物については、居住用でも賃貸用でも固定資産税評価額で評価されますが、居住用家屋の一部を賃貸している場合は、借家権割合×賃貸割合分の評価減を受けられます。
さらに、課税価格を計算する際に、小規模宅地等の特例として、被相続人の居住用宅地の330m2までと、事業用宅地の400m2までについては、配偶者や要件を満たす親族などが相続する場合には、相続税評価額の80%を減額することができます。同様に、賃貸アパートなどの貸付事業用宅地については、200m2までが50%を減額することができます。
(5)基礎控除と特例
最後に、課税価格の合計から、基礎控除として3,000万円+600万円×nを控除することができます。控除後の課税遺産総額を、法定相続割合で按分して、それぞれに相続税率を掛けて相続税額を求め、合算します。さらに、合算した相続税額を、実際にそれぞれの相続人が相続する財産に相当する課税価格の比率で按分したものが、相続人それぞれが納税すべき相続税額となります。
ここで、配偶者が相続する財産については、法定相続分か1億6,000万円のどちらか多い金額まで、相続税を非課税とする税額軽減の特例があります。また、未成年の法定相続人が課税される場合には、未成年者控除として10万円×(18歳-年齢)が税額から控除されます。一方で、配偶者と子(代襲相続人を含む)、父母以外の相続人、例えば兄弟姉妹や孫などが相続人の場合は、税額が2割加算されます。
なお、先の小規模宅地の特例、配偶者の特例を利用する場合は、適用することで税額がゼロになったとしても、申告は必要ですので注意してください。また、遺産分割が成立して、相続分が確定していることも適用の要件となっています。
(6)相続対策
以上より、純粋に節税の観点での相続対策としては、控除額を増やす、相続財産そのものを減らす、課税価格(評価額)を減らす、税額を減らすなどがあることが判ります。
最も取り組みやすい方法としては、資産を分割して早めに生前贈与を行い、相続財産を減らすことです。住宅取得等資金、教育資金、結婚・子育て資金について、直系尊属からの一括贈与の一定額が非課税になる特例や、暦年贈与での110万円の基礎控除がありますので、最大限利用して世代間の資産移転を進めるとよいでしょう。
課税価格を減らすには、資産を不動産として所有することも効果があります。ただし、小規模宅地の特例を適用したいのか、できるのかはよく確認してください。また、税額を減らすには、(5)で述べた配偶者の税額軽減を利用する方法があります。ただし、配偶者に相続財産を集めると、配偶者の相続の際に、逆に課税価格が大きくなったり、法定相続人の人数が減って控除や遺産分割のメリットが薄くなるため、トータルでお考え下さい。
控除額を増やす方法として、法定相続人ではない孫などを養子にする対策もよく言われますが、法定相続人としてカウントできる人数に制限があったり、代襲相続人でない孫が養子になった場合には、税額が2割加算されるなどのデメリットもあるため、こちらも事前によくお確かめください。
関連記事
「相続における配偶者居住権の評価額と節税」
「過剰な保障を防ぐ収入保障保険」
「贈与税の暦年課税と相続時精算課税」
「贈与税の特例」
「配偶者の相続税の減額」
(出典:「相続税のあらまし」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sozoku-tokushu/souzoku-aramashih30.pdf)、
「令和3年分相続税の申告事績の概要」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2022/sozoku_shinkoku/pdf/sozoku_shinkoku.pdf)を元にライフプラン・シム作成)