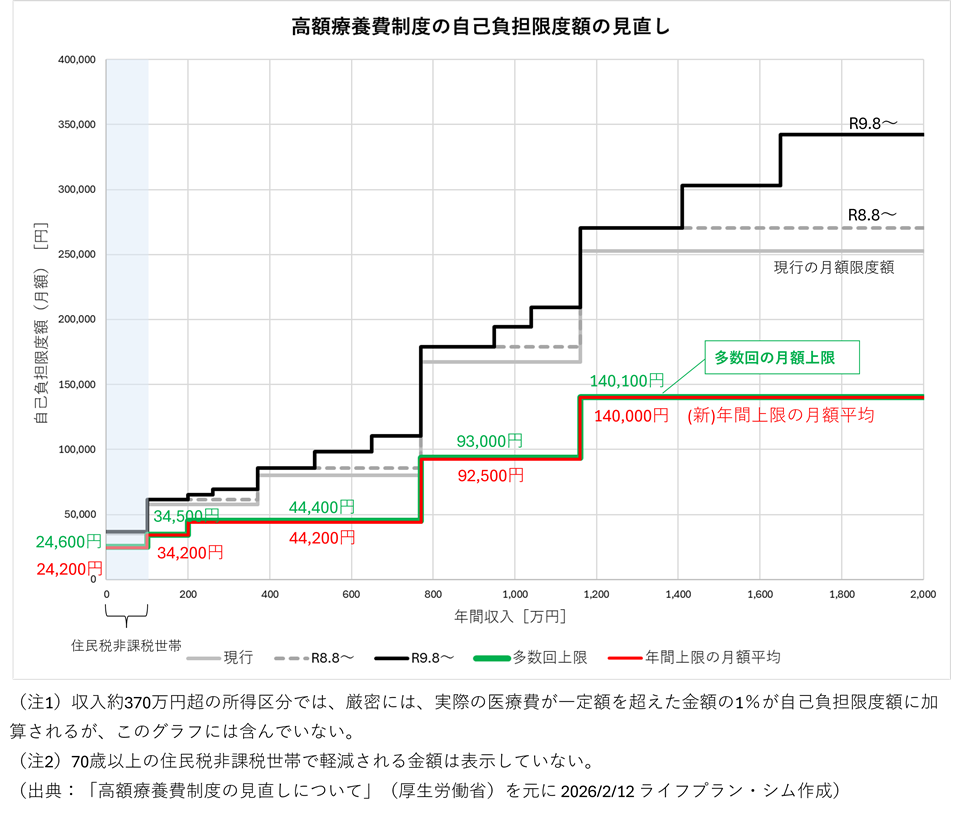令和7年度の税制改正、年金制度改正法案が可決されました。この記事では、iDeCoに関係する改正内容について取り上げます。
拠出限度額の引上げ
会社員や公務員の方がiDeCoに加入する場合には、他の年金制度への加入有無によって、iDeCoへの拠出額に独自の上限が設けられています。昨年(令和6年)12月には、確定給付企業年金(DB年金)にも加入する方のiDeCoへの拠出限度額が、月額12,000円から20,000円に引上げられたばかりでした。昨年12月以降のiDeCoへの拠出限度額を、上の図のピンク色の部分”iDeCo月額〇〇万円”で示しています。
今回の改正では、このiDeCo独自の拠出限度額が、他の年金制度への加入、未加入にかかわらず撤廃され、他の年金制度と合わせた共通の拠出限度額まで拠出可能になります。図ではピンク色の下矢印で示しています。
ただし、国民年金第3号被保険者(厚生年金被保険者の扶養配偶者)の限度額に変更はありません。また、企業型DC年金の事業主の拠出額に上乗せする加入者掛金(マッチング拠出)は、事業主の拠出額を超えられない制限がありましたが、これも撤廃されます。
さらに、この共通の拠出限度額が一律7,000円引上げられ、国民年金1号被保険者(国民年金被保険者)は、これまでの68,000円から75,000円に、国民年金第2号被保険者(厚生年金被保険者)は、55,000円から62,000円に引上げられます。図では橙色の上矢印で示しています。
なお、これらの拠出限度額の引上げは、今後3年以内の実施となっています。
加入(拠出)可能年齢の引き上げ
これまでiDeCoに加入できる方は、図の左下に示すように、国民年金や厚生年金に加入している方でした。詳しくは、国民年金に加入している60歳未満の方(国民年金第1号被保険者)、または国民年金に任意加入している65歳未満の方、あるいは厚生年金に加入している65歳未満の方(同第2号被保険者)とその扶養配偶者である60歳未満の方(同第3号被保険者)で、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付を受給していない方でした。
iDeCoの加入可能年齢を過ぎると、新たに掛金を拠出して積立てることはできず、最長75歳未満で老齢給付を受給開始するまでは、積立てた拠出金を運用するだけ(運用指図者)でした。
今回の改正では、図の右下に示すように、iDeCoの加入者、運用指図者であった方が、60歳、あるいは65歳を過ぎて、国民年金や厚生年金に加入していなくても、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付を受給していなければ、70歳まで加入することができるようになります。退職に伴い、企業型DC年金などの他の年金をiDeCoに移換する方も、継続して70歳まで掛金を拠出することができるようになります。
掛金の拠出が継続できることで、積立額を増やせるだけでなく、掛金は社会保険料控除の対象となりますし、加入月数が増えることで、一時金で受給する際の退職所得控除額が増えるなど、節税につながります。
なお、この加入年齢の引上げも、今後3年以内の実施となっています。
一時金受給での5年ルールの延長
確定拠出年金(企業型DC年金やiDeCo)を60歳で一時金として受給して、5年経過した65歳で退職金を受け取る場合は、別の退職所得として見なすことができ、それぞれに退職所得控除が適用されます。
一方、65歳になる年の前年以前に受け取る場合は、同一の退職所得と見なされ、重複している勤務年数(加入年数)に相当する退職所得控除額を、後から受け取る退職金の退職所得控除額から減額しなければなりません。
この調整規定を”5年ルール”(もしくは”前年以前4年以内”)と言います。詳しくは、記事「確定拠出年金の賢い受け取り方」 をご覧ください。
今回の改正では、65歳までの雇用確保の義務化、さらには70歳までの雇用確保の努力目標化を受けて、この”5年ルール”が”10年ルール”に延長されます。この”10年ルール”は、2026年1月1日以降に受け取る退職金、確定拠出年金の一時金などに適用されます。
ちなみに、今回の改正とは関係ありませんが、退職金を受け取った後に確定拠出年金を一時金で受給する場合には、”20年ルール”が適用されます。
(出典:「年金制度改正法が成立しました」(厚労省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html)、
「令和7年度税制改正」(財務省)(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei2025_pdf/zeisei25_01.pdf)、
「令和7年4月源泉所得税改正のあらまし」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2025kaisei.pdf)を元に、ライフプラン・シム作成)