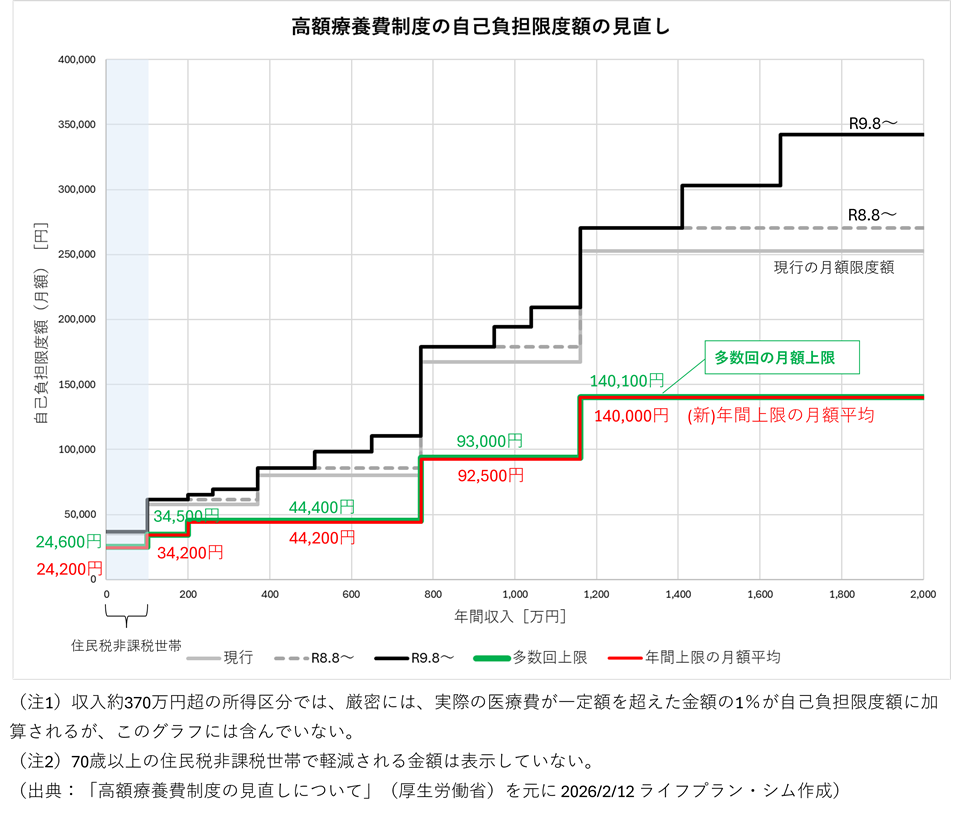世帯の主たる収入者(ここでは世帯主とします)に万一のことがあった場合、残された家族の生計を維持するために、生命保険を検討されるでしょうし、すでに加入されている方も多いと思います。若い人ほど、そのような確率は低くなるものの、子どもの養育費や配偶者の長い人生を支援するためには、多額の生命保険に入らなければならないのが現実です。最も一般的な生命保険としては、一定期間、一定の保険金を保障する掛け捨ての”定期保険”がありますが、保険金額が高くなるほど保険料も高くなるため、家計と相談して保険金額を減らしたりしているのではないでしょうか。
実際には、世帯主の年齢が高くなるにつれて、残された家族が生涯で不足する総額は減少していきます。実際の例は「ライフプランシミュレーションの活用事例」~世帯主に万一のことがあった時の遺族年金はいくらもらえるか~ をご覧ください。そのような傾向に合わせて、年々保障額が一定に減少していくのが”収入保障保険”の特長です(上段のイメージ図)。”収入保障保険”は被保険者が死亡した時点から毎年一定の年金額を保険期間の満了時まで受取るため、死亡年齢が高くなるほど保障金額が減少します(ただし、1年、2年、5年などの最低保証期間あり)。また、死亡保険金を分割して受取ることもあり、一般的に、同等の”定期保険”よりも保険料を抑えることができます。終身保険に付加される特約と、単独の保険商品があり、なかには、非喫煙者やBMI値、血圧値などが良好で健康な方には保険料が割引かれる保険もあります。通常は、被保険者が死亡または高度障害時に支払われますが、身体障害状態や要介護状態で支払われる保険などもあります。
ただし、若い時の支出の状況を細かく見ると、子供の成長に従って支出が増えるため、毎年一定の年金受給では一時的に赤字になる場合がありますので注意が必要です。他にも思わぬ出費があるかもしれませんので、そのようなことが危惧される場合は、総額は90%前後に減少するものの、保険金を一時金として一括で受取ることも検討されるとよいでしょう。また、子どもが独立した後は、万一の場合でも貯蓄と遺族年金などの収入で賄えるようになることもあります。実際にそのようになれば、途中で保険を解約して保険料を節約してもよいでしょう。なお、一般的に”収入保障保険”は掛け捨てで、解約返戻金はありません。
次に、”収入保障保険”を受取る場合の税金についても触れておきます。死亡保険金を一時金として一括で受取る場合は、一時金に対して相続税がかかります。また、年金で受取る場合は、”年金受給権”を年金受取人が相続することになり、相続税がかかります。ここで、”年金受給権”の相続評価額は、(1)解約返戻金の額、(2)一時金として一括で受取る場合の額、(3)年金総額を予定利率の複利で現在価格に割戻した額、のうち最も大きい額となります。イメージ図の例において(2)が該当したと仮定して、世帯主が35歳時点の一時金が年金総額の90%だとすると、”年金受給権”は5,400万円となります。相続人が配偶者と子ども1人のケースでは、死亡保険金については法定相続人の数2×500万円=1,000万円が控除されるため、他に受け取る死亡保険金が無ければ、控除後の”年金受給権”は4,400万円となります。
また、基礎控除として3,000万円+法定相続人の数2×600万円=4,200万円が控除されます。したがって、”年金受給権”4,400万円と他に相続財産があれば合算し、そこから基礎控除4,200万円を差し引いた残り(課税遺産総額)に相続税が課せられます。課税遺産総額がゼロでない場合は、一旦、法定相続人で課税遺産総額を按分してからそれぞれの相続税額を個別計算した後に合算します。死亡保険金の場合は受取人が全て相続するため、実際の相続額の比率に従って合算した相続税額が割り振られます。その上で、配偶者については相続額が(1)法定相続分の金額、(2)1億6,000万円、のどちらか大きい方まで相続税が非課税となる税額軽減特例があります。未成年者については(18歳-相続時の年齢)×10万円を税額から控除でき、例えば、子どもに割り振られた課税遺産額が1,000万円の場合の相続税は100万円ですが、相続時の子どもの年齢が8歳未満であれば、子どもにも相続税はかかりません。
ただし、年金を受取る際には、相続税を課せられなかった部分については、2年目から雑所得と見なされて他の所得と合算され、所得税、住民税が課せられます。上の例では相続税評価割合が90%でしたが、このときの課税対象は年金総額の8%と定められています。下段のイメージ図に示すように、受給回数をn回とすると、8%の金額をn-1回で均等に按分するのではなく、2年目は最終年の1/n-1、3年目は2/n-1・・・となるように段階的に按分されます。つまり、保険契約期間の満了に近づくにつれ雑所得と見なされる額が増えていきます。また、支払った保険料総額のうち年金受給権に相当しない分(この例では10%)についても、それぞれの受給回の所得額に応じて按分して、経費として所得額から控除することができます。
(出典:「相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm)を元に、課税の説明部分について、ライフプラン・シム作成)